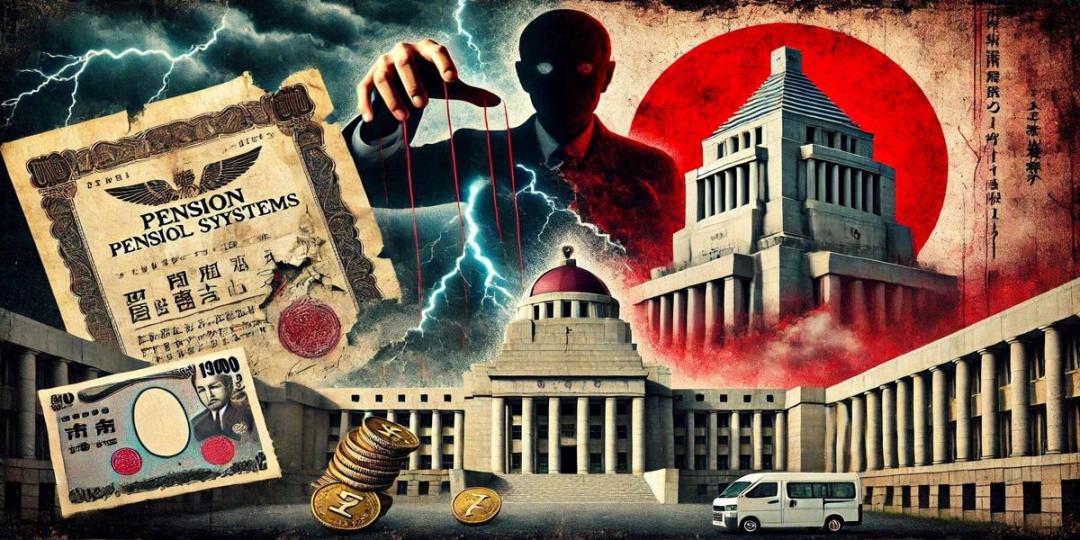|
2025/5/27
|
|
250527_偏向報堂-WHOと厚労行政 |
|
|
「それ、正しいと思ってた?厚労省と年金・医療制度に潜む“見えない罠”」
1.はじめに:その“安心”、本当に正しい? あなたは、年金制度や医療制度について、「国がなんとかしてくれるはず」と思っていませんか? 忙しい日々の中で、制度の仕組みまで深く考える時間はなかなか取れないものです。かつての私もそうでした。「毎月の保険料は自動で引かれているし、将来きっと何とかなる」と、どこか他人事のように感じていたのです。 しかし、ここ数年の変化は、そんな“安心神話”に疑問を投げかけるものでした。社会保険料の急激な上昇、少子高齢化の加速、そして新型コロナを機に露呈した医療行政の混乱と利権構造。 これらは、単なる「一時的な問題」ではなく、私たちの生活基盤そのものを揺るがす重大な兆候です。とくに最近では、2027年から始まる厚生年金保険料の増額や、国民に知らされぬまま進められる「WHOパンデミック条約」の議決など、「知らないうちに進められる重要事項」が目立ちます。 それに対して、報道機関も政治家もほとんど情報を発信していない。そう気づいたとき、私は強い違和感を覚えました。「知らなかった」「仕方ない」と済ませていい問題でしょうか? 本記事では、厚労行政の構造的な問題をわかりやすく解説しながら、あなた自身が現実を正しく理解し、考え、行動できるようになるための視点をお届けします。 ぜひ最後までお読みください。見えていなかった真実が、きっとあなたにも届くはずです。
2.問題提起:ステルス課税と歪んだ行政の構図 あなたは、給料明細の「社会保険料」の欄をじっくりと見たことがありますか? 毎月の手取り額が減っていても、理由を深く考えたことがないかもしれません。実は今、私たちは気づかないうちに“見えない税金”=ステルス課税によって、着実に負担を増やされています。たとえば、2027年9月から施行予定の厚生年金保険料の引き上げでは、年収798万円を超える会社員を対象に、月額約9,000円の負担増が計画されています。これは年間で10万円を超える出費となります。しかし、この変更が大きく報道されたことはあったでしょうか?さらに2026年には「在職老齢年金」制度の見直しが予定されており、高齢者が働きながら年金を受け取る際の基準額が引き上げられることで、実質的な給付削減も進められようとしています。 これらは一見、制度の合理化や世代間の公平を目的としているように見えますが、実際には国民の理解や合意形成が不十分なまま進められている点に大きな問題があります。 加えて、2025年5月にWHOで採択された「パンデミック条約」においても、日本政府は国民に向けた十分な説明や議論を行っていません。この条約は、将来の感染症対策を国際的に連携するという建前のもと、国内政策への影響も否定できない重要な内容を含んでいます。にもかかわらず、多くの人々はこの事実を知りません。そして、メディアもまた、積極的にこの話題を取り上げようとはしないのです。 私たちが知らされないまま、じわじわと進められる制度変更や国際条約。 その背景には、国民の無関心と、政治・行政の“説明しない文化”があるのではないでしょうか。こうした見えにくい形で進む負担増や政策変更にこそ、しっかりと目を向けなければならない時代が来ています。
3.問題の要因分析:制度が壊れる理由:人口構造・利権・統計操作 年金制度や医療制度が限界を迎えつつある主な理由は、単に「少子高齢化だから」という一言で片づけられるものではありません。もっと深い構造的な問題が、静かに制度を蝕んでいるのです。 第一に、人口構造の崩壊があります。現在の日本は、現役世代が高齢者を支える「付加方式」という年金制度を採用しています。しかし、少子化と高齢化が急速に進んだ結果、この仕組みそのものが成り立たなくなりつつあります。若い世代の負担が増え続け、高齢者1人を支えるために必要な現役労働者の数はすでに危機的水準です。さらに問題なのは、厚生労働省がこの現実を過小評価している可能性です。たとえば出生数について、将来推計が現実よりも楽観的に見積もられていたとする分析もあり、制度設計が実態から乖離していたのではないかという疑念があります。制度が破綻しても「予想外だった」と言い逃れるために、最初から甘い数字を使っているのではないか──そう考える専門家も少なくありません。 第二に、既得権益と利権構造の存在です。とくに厚労省内にいる「医系技官」と呼ばれる官僚たちは、国家公務員試験を経ずに医師免許を持つことでキャリアポストに登用される特別枠の存在です。彼らはその専門性ゆえに政治家からも干渉を受けにくく、行政判断の透明性が極めて低いまま、重要な制度設計に関わっています。実際、コロナ禍では「PCR検査の拡大を意図的に抑制した」「幽霊病床を設けて補助金を不正受給した」といった報道が相次ぎました。これは単なる失敗ではなく、利権を守るための“意図的な判断”だったのではないかとすら言われています。また、医療や感染症対策の分野には「医療村」「感染症村」と呼ばれるような、官僚・業界団体・政治家が結託した構造が存在します。こうした利権集団が制度改革を阻み、自らの既得権を守るためにあらゆる手段を講じているのです。人口構造の変化に目を背け、統計をごまかし、利権を守るために制度を歪める。──これが、今の日本の年金制度と医療行政が抱える“見えない破綻”の正体です。
4.国民の声:無関心という最大のリスク 厚生労働省の政策や年金・医療制度の問題が、ここまで深刻な状態になっている背景には、国民の“無関心”というもう一つの大きなリスクが存在しています。毎月の給与から引かれる社会保険料や税金について、あなたはその使い道を把握していますか? 会社が代行して納付し、明細にもあまり細かく記載されないこの仕組みは、「よく分からないけど引かれている」状態を生み出しています。 この構造こそが、国民を“自動的に従うだけの存在”に変えてしまう原因です。そして、この仕組みによって、政府や官僚たちは「説明しない」「議論をしない」ことが常態化していきました。SNSでは、こうした状況に疑問を抱いた人々の声も増えつつあります。「毎年のように保険料が上がるけど、将来ちゃんと年金もらえるの?」 「厚労省の発表って、いつも専門用語ばかりで分かりにくい」 「WHOで決まった条約って、国会で審議されたの?聞いたこともない」 このように、「知りたいのに知らされない」ことへの不信感や不安が、じわじわと広がっているのです。 一方で、報道機関や大手メディアがこれらの問題を深掘りして報じることはほとんどありません。医療業界や官僚組織とのしがらみ、あるいはスポンサー企業の意向が影響しているのかもしれません。いずれにしても、「大切な情報ほど、表に出ない」状態が続いているのです。 その結果、制度の裏にある構造や利権について考える人は少なく、「気づいた頃にはもう手遅れ」という事態が現実になりつつあります。私たちが制度に無関心でいること自体が、政治や行政の“無責任”を助長しているのかもしれません。無関心という姿勢が、結果として自分や家族の首を絞めることになってはいないでしょうか?「知らないうちに決まっていた」「気づいた時には変えられない」──そんな悔しさを味わわないためにも、今こそ制度の裏側に目を向けるべき時です。
5.では、どうすればいい?:制度を正すために私たちができること 問題の大きさに気づいたあなたは、きっとこう感じているかもしれません。 「結局、個人にできることなんてあるのだろうか?」と。たしかに、年金制度や厚労行政の改革は、一朝一夕で実現できるものではありません。ですが、変化は“無関心をやめること”から始まります。 ここでは、あなたが今から実践できる3つのアクションを提案いたします。 1)制度の仕組みを“知る”ことから始める まずは、社会保険料や年金の仕組みについて基本的な理解を持つことが重要です。 「会社が払っているから」「毎月天引きされるから」と他人事にするのではなく、自分のお金がどこへ行き、何に使われているのかを一度見直してみてください。たとえば、手取りだけでなく、雇用者負担分を含めた「総支給額」に対してどれだけの負担が発生しているのかを知るだけでも、社会の構造が違って見えてきます。 2)“説明しない政治”に声を上げる 2025年5月に採択されたWHOの「パンデミック条約」は、日本にとって重大な影響を及ぼしかねない国際合意です。 にもかかわらず、国会でのまともな議論もなく、メディアでも大きく報じられていません。こうした「知らせない・議論しない・勝手に決める」政治と行政の姿勢に対しては、声を上げることが必要です。 SNSでの発信、地元議員への問い合わせ、署名活動への参加など、小さなアクションでも積み重ねれば力になります。 3)正しい情報にアクセスし、周囲と共有する 大手メディアだけでなく、信頼できる個人や団体の発信にも耳を傾けましょう。 また、得た情報を家族や友人と共有することで、「知っている人」を増やすことも大きな意義があります。とくに小規模事業主のような立場にある方は、税や保険料の仕組みにもっと関心を持ち、自衛手段を整えることが、事業の持続性にも直結します。
制度を変えるのは、結局のところ“関心を持つ人”です。 その第一歩として、あなたが「知る」「伝える」「動く」こと。 これが、未来を守る最も確実な方法なのです。
6.まとめ:無関心からの脱却が未来を変える ここまでお読みいただき、ありがとうございます。 年金制度や医療制度、そして厚労行政に潜む問題を見てきて、あなたはどのような感情を抱かれたでしょうか。制度の仕組みが複雑であること、情報が十分に開示されていないこと、そして利権によって変化が阻まれていること。 これらはすべて、「知ろうとしなければ見えない」ように作られています。だからこそ、無関心でいる限り、制度は静かに、しかし確実に私たちの生活を圧迫していきます。でも逆に言えば、「知ること」「疑問を持つこと」「声をあげること」こそが、状況を変える最大の力なのです。 厚労省の保険料引き上げ、WHOのパンデミック条約、医系技官の利権構造――。 これらの事実を知ったあなたには、すでに「変化を起こす側」になる準備が整っています。未来を他人任せにせず、自分の頭で考え、行動する。 それが、あなた自身と、あなたの大切な人たちの暮らしを守る最も確かな方法です。無関心を手放したとき、私たちの未来は変わり始めます。 どうか、今日からその一歩を踏み出してみてください。
7.関連記事の紹介 この記事を通じて、「厚労行政の裏側にある構造的な問題」や「国民の無関心が生むリスク」に気づいたあなたへ。 さらに深く学び、理解を深めていただくために、以下の関連記事をぜひご覧ください。どれも今回のテーマとつながりが深く、あなたの思考をさらに進めてくれるはずです。
1)「厚労省の構造的問題とは?医系技官と利権の関係を読み解く」 厚生労働省の意思決定を陰で左右する“医系技官”とは何者なのか? その採用制度の特殊性や、政策への影響、利権構造との結びつきについて詳しく解説しています。
2)「WHOパンデミック条約の全文解説と日本の対応」 2025年に採択されたパンデミック条約の中身とは何か? 条約の核心部分や、国家主権に関する重要な条項、日本国内での議論状況について丁寧にまとめた記事です。
3)「なぜ国民の声が政治に届かないのか?無関心が生む民主主義の危機」 選挙に行っても変わらないと感じていませんか? 国民の関心が薄い分野でこそ、既得権が温存されやすくなります。政治と距離を置いたままだとどうなるのかを解説します。
4)「ステルス課税とは?見えない増税のメカニズム」 年金・医療・社会保険料に潜む“隠れた税金”の仕組みを、実例を交えてやさしく解説します。給与明細の見方が変わるかもしれません。
5)「あなたの知らない“医療村”の正体」 コロナ禍で浮き彫りになった“医療村”の実態とは? 医療界・官僚・政治家が絡む閉鎖的な世界にスポットを当てます。
どの記事も、あなたが“知らなかったでは済まされない現実”に一歩近づくためのヒントとなるはずです。 制度に振り回される側から、制度を見極め、変える側へ。 引き続き、あなたと共に考えていけることを願っています。 以上です。 |
|
| |